屋上の怪人
タコ入道のような火星人と、電気ロボットが東京にあらわれたことは、新聞の大きな記事によって、日本じゅうに、知れわたりました。
中村、有田、長島の三少年を驚かしたのちにも、この二つの恐ろしい怪物は、東京の方ぼうにあらわれました。そして、その怪物がきえうせたあとには、いつでも、「月世界旅行をしましょう」とか、「月世界へおいでなさい」とかいう、みょうなことを書いた紙きれが落ちているのでした。
あるときは、銀座のビルの電光ニュースに、とつぜん「月世界へいきましょう」という文句が流れて、大ぜいの人びとを、びっくりさせたこともあります。
また、あるときは、銀座通りの広告塔のラウド・スピーカーから、やっぱり、「月世界へおいでなさい」という声が、くりかえしてさけばれ、人びとをふしぎがらせたこともあります。
何者かが、東京じゅうの人を、月世界へさそっているようです。いったい、だれが、なんのために、そんなことをやっているのでしょう。
さて、そんなさわぎの起こっている、ある日のこと、明智探偵事務所の小林少年のところへ、へんな電話がかかってきました。
「きみは小林君だね。ぼくはデンジンMというもんだ。」
「え、どなたですか。」
「デンジンM。」
「デンジンって?」
「電気の電と、人物の人だ。電気の人間という意味だ。電人Mというのが、ぼくの名だ。」
小林君はだれかが、からかっているのかと思いました。
「その電人Mが、ぼくになんの用があるのですか。」
「きみに会いたいのだ。」
「どんな、ご用ですか。」
「電話では言えない。会ってから話す。きょう午後四時きっかりに、日本橋のMビルの屋上へきてもらいたい。ぼくは屋上で待っているからね。」
Mビルというのは、一階に銀行があって、二階から六階まで、いろいろな会社の事務所がある、大きなビルでした。小林君は、そのビルをよく知っていました。
「そこで、きみにおもしろいものを見せてあげる。これは電人Mの挑戦だよ。もし、きみがMビルへこなければ、きみは、ぼくに負けたことになるのだ。」
挑戦と言われては、相手が何者であろうとも、あとへひくことはできません。小林君は四時にMビルの屋上へいくことを約束して、電話を切りました。
それから、明智先生と相談して、ともかくMビルへ行ってみることにしました。いつもなら電車に乗るのですが、きょうは自家用車を、自分で運転していくのです。
「仮面の恐怖王」の事件で、小林君とポケット小僧は、山の中にうずまっていた、ばくだいな小判を発見して、そのお礼として、少年探偵団へ五百万円の寄付がありましたので、そのお金で、探偵事務所に無電の設備をして、十個の携帯無線電話をそなえつけました。その小さな箱を持っていれば、どこからでも、探偵事務所と話ができるのです。
それから、一台の自動車を買い入れました。「アケチ一号」という名前です。それは探偵用の自動車で、腰掛けの下に人間がかくれることもできますし、また、そこには、いろいろな変装の道具もいれてあるのです。携帯無線電話の箱も、おいてあります。自動車にとりつけないで、いつでも持ちだせるようになっているのです。
小林君は、まえから自動車の運転ができたのですが、このアケチ一号を買ってから、その車でじゅうぶん、練習しましたから、すこしもあぶなげがありません。小林君はアケチ一号を運転して、日本橋のMビルの前に車をとめておいて、エレベーターで屋上にのぼりました。まだ四時には二―三分あります。
広い屋上には、人かげもありません。昼ごはんのあとは、会社の人でにぎわうのですが、いまはもう夕方に近いので、だれも屋上にあがっている人はないのです。屋上には、両方のはしに、出入口がついています。小さな小屋のようなもので、そこにエレベーターと階段があるのです。
腕時計が、ちょうど、四時をさしたとき、そのいっぽうの出入口のドアが開いて、変なものが出てきました。
大きなロボットです。からだは鉄でできているようです。頭は、すきとおったプラスチックで、その中に機械がいっぱいならんでいます。二つの赤い光が、チカッ、チカッと、ついたり消えたりしていて、それが赤い目のように見えるのです。
「あっ、あいつが、電人Mだなっ。」
小林君は、とっさに、そう考えました。そして、じっと、待っていますと、ロボットは、機械のような歩き方で、こちらへ進んできました。
「おお、小林君、よくきたね。いまに、おもしろいことが、はじまるから、見ていたまえ。」
ロボットが、へんなしわがれ声で、言いました。
小林君は、こいつが新聞に出ていたあのロボットだなと、思いました。風船のように、空へとんでいった、あのロボットと同じやつだろうと、考えたのです。
ロボットは、屋上の手すりのところへいって、はるか下の道路を見おろしました。
そこには、都電が通っています。たくさんの自動車が、走っています。それがマッチの箱のように小さく見えるのです。人道には、豆粒のような人が、ゾロゾロと歩いています。
ロボットは、右手に、厚ぼったい紙のたばを持っていましたが、その右手を、たかくあげたかとおもうと、紙たばを、パッと、下の道路にむかって、投げおろしました。
紙が一枚一枚はなれて、ひろがって、まるで雪のように、チラチラと降っていきます。美しいながめです。下の道路を歩いていた人たちが、それに気づいて、空を見あげています。両手をひろげて、待ちかまえている人もあります。
白い紙きれは、人びとの頭の上をかすめて、地面に落ちました。みんなが、争ってそれを拾っています。その紙きれには、
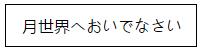
と、印刷してあったのです。
この紙を投げたのは、だれだろうと、みんながMビルの屋上を見あげました。
ロボットは平気で、手すりによりかかって、下をのぞいています。
地面からワーッという声が、聞こえてきました。みんなが、恐ろしいロボットを見て、さけんでいるのです。
やがて、向こうから、ふたりの警官が、かけつけてきました。そして、Mビルの入口から、中へはいってくるのが見えました。それでも、ロボットは、もとの姿勢のまま、動くようすはありません。
いまに、あの警官が屋上にあがってきたら、どうするだろうと、かえって小林君のほうがしんぱいになるほどでした。
それから、いきづまるような数分間がすぎました。
すると、はたしてむこうの出入口から、ふたりの警官と、おおぜいの背広の人たちがかけだしてきました。
「あっ、あそこにいる。」
だれかが、大きな声でさけびました。
そのときロボットは、やっとてすりをはなれて、人びとのほうを見ました。
「小林君、いいかい。これから、おもしろいことがおこるんだ。きみのちえをはたらかせるときだよ。」
そういったかとおもうと、ロボットは、やにわにむきをかえて、べつの出入口のほうへかけだしたのです。機械のようなへんなはしりかたですが、その早いこと。
小林君もあとをおって、かけだしました。小林君はむろん、警官のみかたです。
警官たちは、ロボットがにげだすのを見て、いっそう足を早めたので、だんだんへだたりがちぢまってきます。
ロボットは階段をかけおりて、六階におり、そこの廊下をはしっていって、ひとつの部屋にとびこむと、中からかぎをかけてしまいました。小林少年はドアのまえに立ったまま、みんなのくるのをまっているほかはないのでした。


