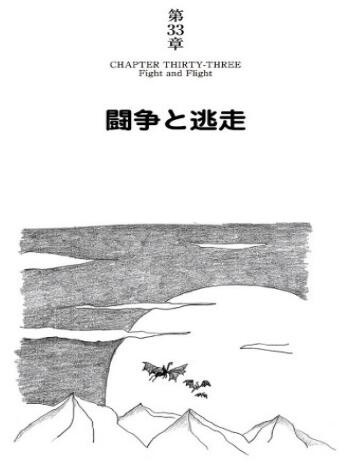
ハーマイオニーがいったい何を企くわだてているのか、いや、企てがあるのかどうかさえ、ハリーには見当もつかなかった。アンブリッジの部屋を出て、廊下ろうかを歩くとき、ハリーはハーマイオニーより半歩遅おくれて歩いた。どこに向かっているのかをハリーが知らない様子を見せたら、疑われるのがわかっていたからだ。アンブリッジが、荒い息遣いきづかいが聞こえるほどハリーのすぐ後ろを歩いているので、ハリーはハーマイオニーに話しかけることなどとうていできなかった。
ハーマイオニーは階段を下り、玄げん関かんホールへと先導せんどうした。大広間の両開きの扉とびらから、大きな話し声や皿の上でカチャカチャ鳴るナイフやフォークの騒音が響ひびいてきた。――ハリーには信じられなかった。ほんの数メートル先に、何の心配事もなく夕食を楽しみ、試験が終ったことを祝いわっている人がいるなんて……。
ハーマイオニーは正面玄関の樫かしの扉をまっすぐに抜け、石段を下りて、とろりと心地よい夕暮れの外気の中に出た。太陽が、禁じられた森の木々の梢こずえにまさに沈もうとしていた。ハーマイオニーは目的地を目指し、芝生しばふをすたすた歩いた――アンブリッジが小走りについて来た――三人の背後に、長い影がマントのように芝生に黒々と波打った。
「ハグリッドの小屋に隠されているのね」アンブリッジが待ち切れないようにハリーの耳元で言った。
「もちろん、違います」ハーマイオニーが痛烈つうれつに言った。「ハグリッドが間違えて起動きどうしてしまうかもしれないもの」
「そうね」アンブリッジはますます興こう奮ふんが高まってきたようだった。「そう、もちろん、あいつならやりかねない。あのデカぶつのうすのろの半人間め」
アンブリッジが笑った。ハリーは振り向いて、アンブリッジの首根くびねっこを絞しめてやりたいという強い衝しょう動どうに駆かられたが、踏ふみ止とどまった。柔らかな夕ゆう闇やみの中で、額ひたいの傷きず痕あとが疼うずいていたが、まだ灼しゃく熱ねつの痛みではなかった。ヴォルデモートが仕し留とめにかかっていたなら激痛げきつうが走るだろうと、ハリーにはわかっていた。
「それじゃ……どこなの」ハーマイオニーが禁じられた森へとずんずん歩き続けるので、アンブリッジの声が少し不安そうだった。
「あの中です、もちろん」ハーマイオニーは黒い木々を指差した。「生徒が偶然ぐうぜんに見つけたりしないところじゃないといけないでしょう」
「そうですとも」そうは言ったものの、アンブリッジの声がこんどは少し不安げだった。「そうですとも……結構けっこう、それでは……二人ともわたくしの前を歩き続けなさい」
「それじゃ、先生の杖つえを貸かしてくれませんか 僕たちが先を歩くなら」ハリーが頼んだ。
「いいえ、そうはいきませんね、ミスター・ポッター」アンブリッジが杖でハリーの背中を突きながら甘ったるく言った。「お気の毒だけど、魔法省は、あなたたちの命よりわたくしの命のほうにかなり高い価値をつけていますからね」


